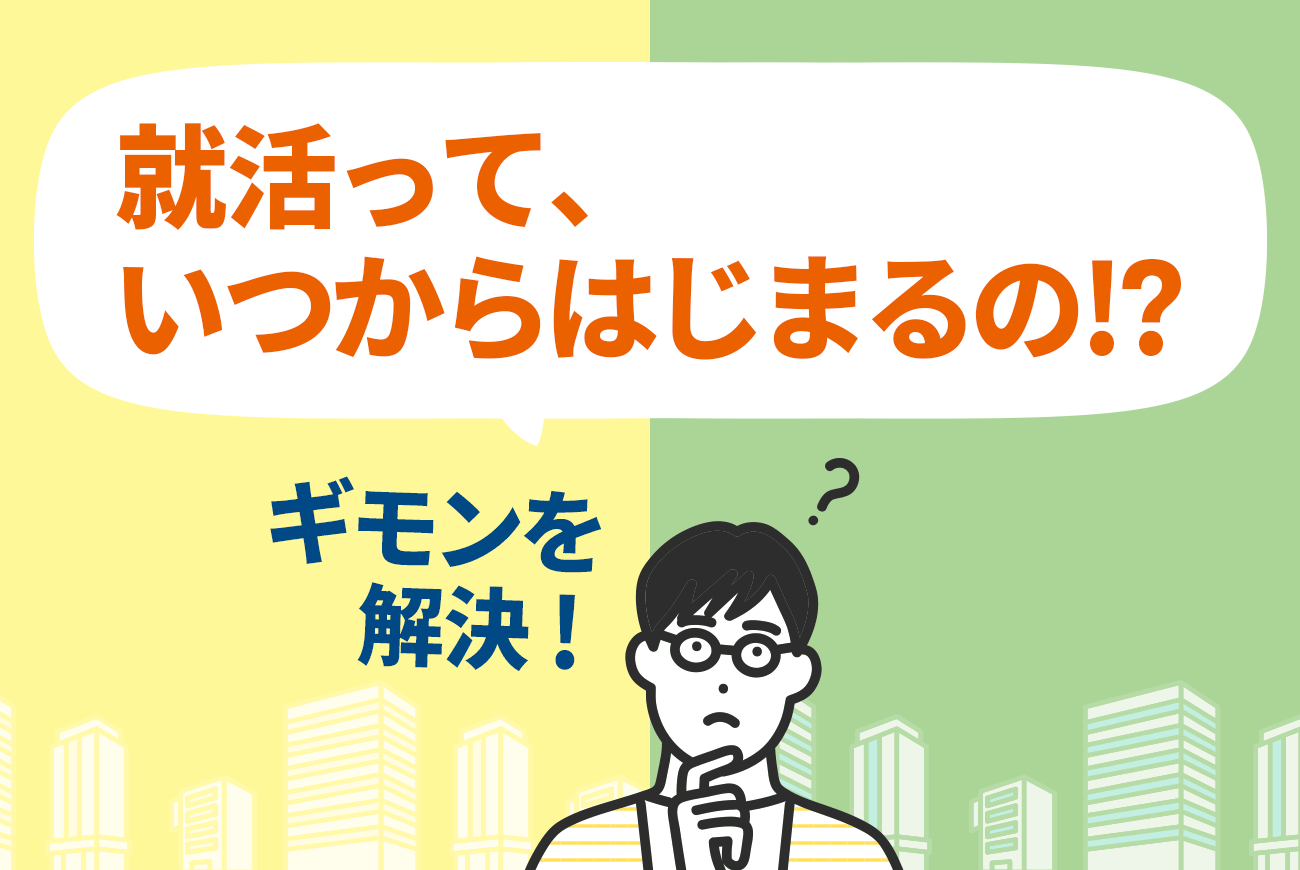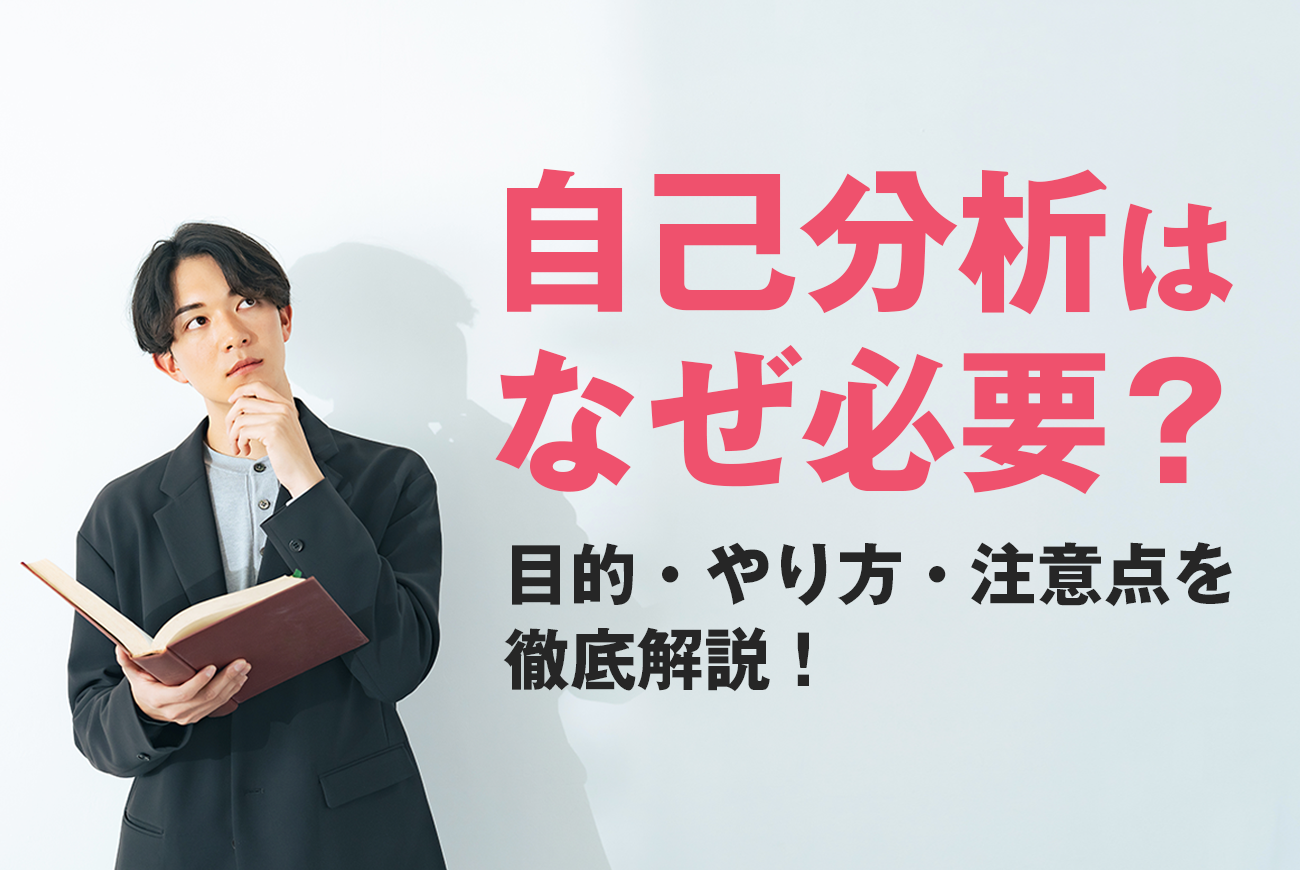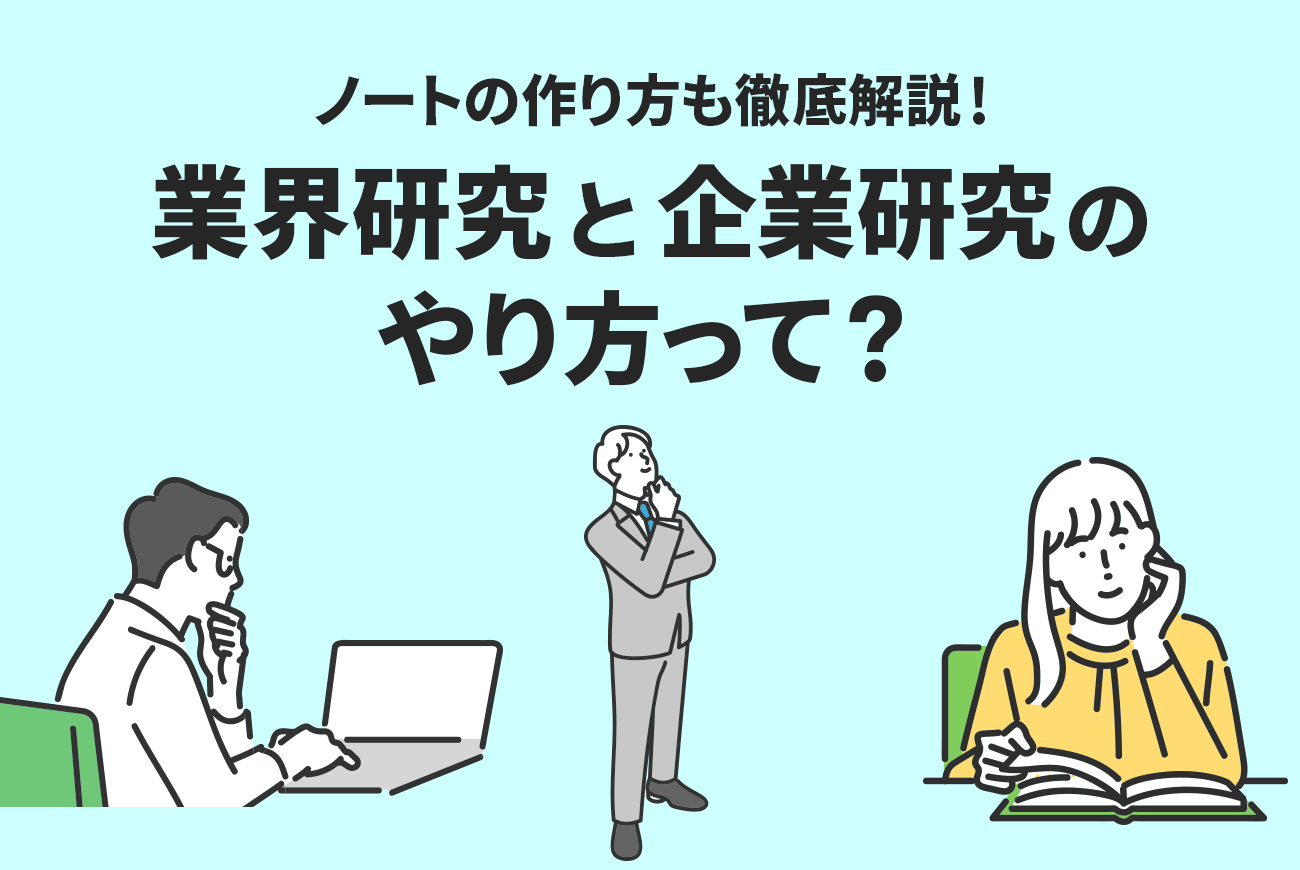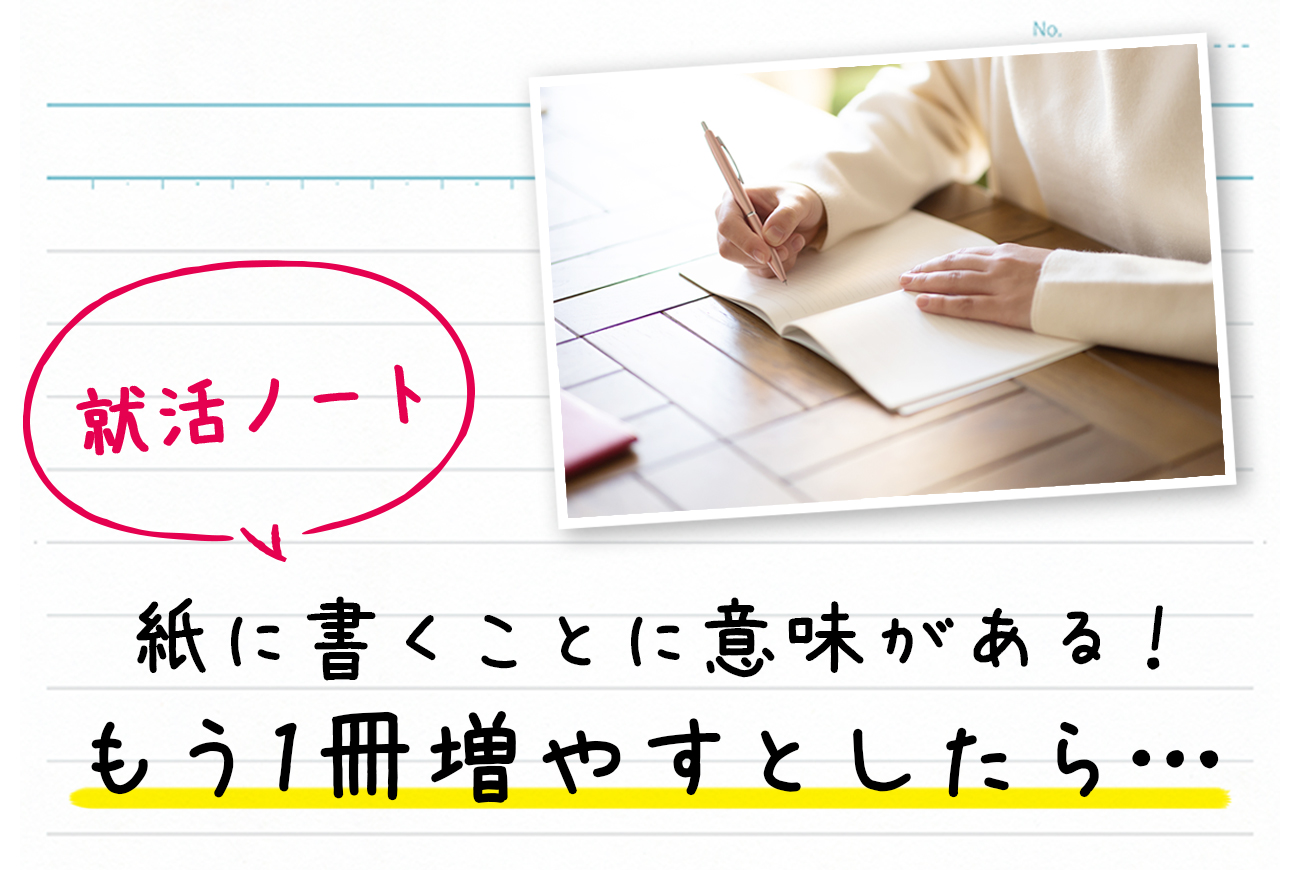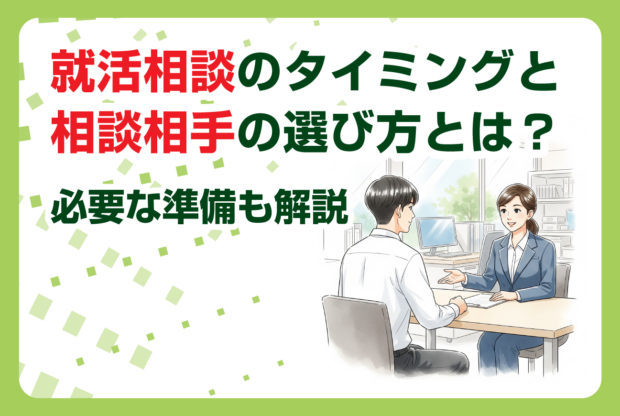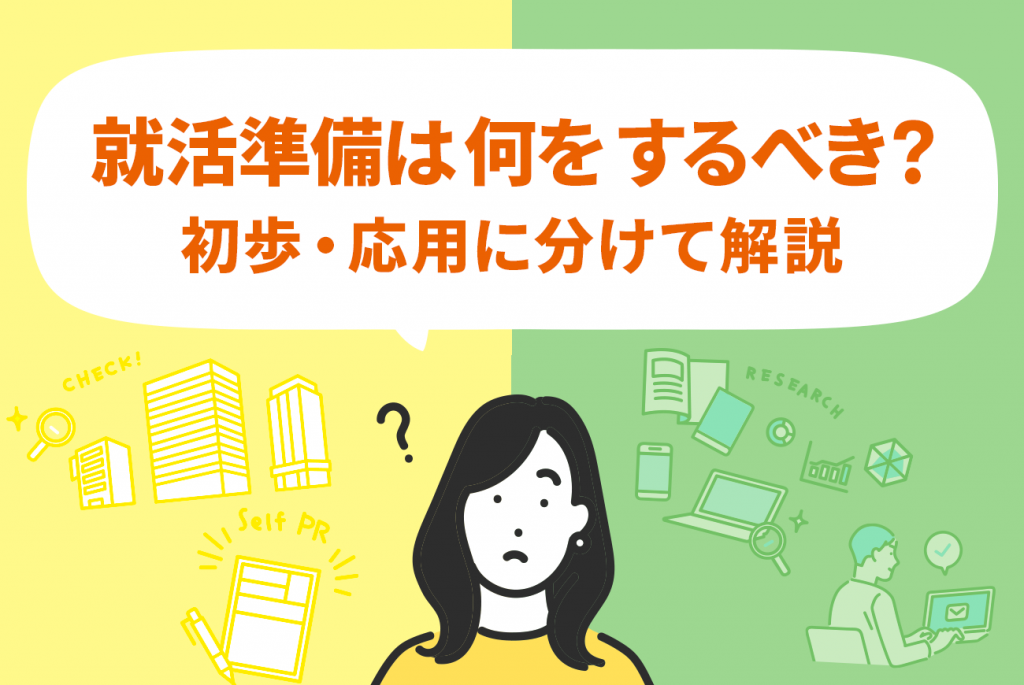
「就活のために何をすればいいか、端的に情報を知りたい」 そんなニーズに応えて、この記事では、就活準備に関する情報を「初歩」と「応用」に分けて紹介します。この記事を最後まで読めば、余裕をもって就活を迎えられるでしょう。就活で成功したい人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
就活準備には3種類ある
まず、就活準備には「企業が求める人材に自分がなるための準備」と「自分が行きたい企業を見つけるための準備」「本格的な就活に向けた実践のための準備」といった3種類に分けられることを理解しておきましょう。大学1年生の頃から就活準備は始まっているので、しっかり知識を得ておくことが大事です。
企業が求める人材に自分がなるための準備(1年〜3年生前半)
志望企業から内定を獲得するためには、企業が求める理想の人物像を意識する必要があります。企業側は、自社で活躍してくれそうな学生を採用したいと考えているからです。理想の人物像は企業によって異なるためあくまで一例ですが、代表的なものを紹介します。
・学業の成績が優秀であること:目標達成のために努力するスキルがあると判断されやすいから。よって、就活だけでなく学業にも力を入れるとよい。明確なデータが提示できるように、資格取得や賞の受賞を目指すこともおすすめ
・コミュニケーションスキルが高いこと:社会人は、業務において他者とかかわる機会が多いから。サークル活動、アルバイト、インターンなど他者と触れ合う経験を積み、コミュニケーションスキルを向上させることをおすすめする。なお、経験にオリジナリティがあるとさらによい
・ものごとに対して積極的に取り組むこと:自分から動いて仕事を探せる人材は新たなビジネスチャンスを生みやすいから。常日頃から、自分にできることを探しながら行動するように意識するとよい
さまざまな準備を進めながら、「企業側が求めているものは何だろう?」と考え、理想的な人物を目指しましょう。
自分が行きたい企業を見つけるための準備(1年生から3年生末)
就活では、自分が本当に行きたい企業を探すことが重要です。魅力的な企業を見つけられたら、就活準備に力が入りやすくなるでしょう。「給料が高い企業」「人気のある企業」を目指すだけでなく、自分が心から「働きたい!」と思えるような企業を、就活準備を通して探してみてくださいね。
本格的な就活に向けた実践のための準備
「企業が求める人材に自分がなるための準備」と「自分が行きたい企業を見つけるための準備」がある程度終えられたら、これから始まる本格的な就活に向けた実践的な準備を始めます。
具体的に言うと、就活全体のスケジュールを把握することが求められるでしょう。インターンシップ(インターン)、説明会、選考などの企業ごとの日程を確認し、どの企業にエントリーするか決めていきます。ここでしっかりとスケジュールを組んでおくことで、本格的に就活が始まっても焦らずに済むはずです。
また、スケジュールの把握と並行しながら、自分自身の深掘りをして企業選びの参考にする「自己分析」や、志望する企業について詳しく調べる「企業研究」などにも取り組んでおくといいでしょう。
これに加え、企業側と関わる際の印象をアップするために、身だしなみを整えることも必要です。たとえば、「就活用のスーツを手に入れておくこと」「正しい身だしなみや服装は何か調べておくこと」などが例に挙げられるでしょう。 企業からの印象を高めるという意味では、基本的なビジネスマナー(はっきりとしたあいさつやていねいな言葉遣いなど)を学んでおくことも重要になってきます。
就活準備の初歩
ここからは、就活準備の中でも「初歩」に含まれる情報を紹介します。
就活開始のタイミング
2025卒の場合、説明会などが開始される時期が3月1日以降、面接などが始まる時期が6月1日以降とされています。
参考:2025(令和7)年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程(厚生労働省)
しかし、業界や企業によっては、独自のスケジュールを選択することも。よって、就活をスタートさせるタイミングは、人によって変わります。自分が希望する企業の就活スケジュールを調べ、余裕を持った準備ができるようにしてください。 より詳しい情報を知りたい人は、こちらの記事にもアクセスしてみましょう!
自己分析の方法
自己分析は、就活を進めるにあたって重要度が高い準備です。
自己分析:自分の性格や行動パターンから、自身の強み・弱み・特徴などを把握すること
自己分析を進めることで、「企業側に対してどのようなアピールができるか」がわかってきます。また、「自分に適した企業の特徴は何か」もつかめてくるでしょう。結果的に入社後のミスマッチも防げるため、就活準備の第一歩目としてぜひトライしてみましょう。
具体的な自己分析方法は、以下の通りです。
・自分史を作成する
・モチベーショングラフを作成する
・友人や家族へ自分に関するインタビューを行う
・自分自身に質問を行う
複数の方法に取り組み、より内容を充実させることもおすすめします。
業界・企業研究のポイント
自己分析が終わったら、業界研究・企業研究を行いましょう。気になる業界や企業について知識を得ることで、自分に適性があるかどうか把握できるからです。
【業界研究】
・在籍する企業
・各企業の関係性
・将来性
・トレンド
【企業研究】
・企業名
・事業内容
・仕事内容
・社員の特徴
・社風
ホームページや書籍を参考にして、上記のような内容を各業界・企業ごとに調査しましょう。
スーツを買う
企業や業界によって指定される服装に違いはありますが、リクルートスーツは購入しておいた方がいいでしょう。もし予算に余裕があるなら、汚れてしまったときのことを考えて複数枚用意しておくと安心です。

就活準備の応用
次に、取り組んでおくとまわりに差がつけられるかもしれない就活準備の「応用」を解説します。
インターンに参加する
インターンとは、就業体験を通して学生が企業の業務に携わることを指します。開催期間は企業によって異なり、1日で終わるもの~数か月以上のものまでさまざまです。興味がある業界・企業のインターンに参加することで、就活の知識を深められるでしょう。選考直結型のインターンもあるため、参加しておいて損はないはずです。
ちなみに、インターンに参加する際は、事前に細かなスケジュールを把握しておくことも求められます。なぜなら、複数のインターンに参加する場合、他社同士のインターンの日程が被ってしまう可能性があるからです。詳しいスケジュールがわからない場合は、企業の担当者に質問しておくと安心ですよ。
社会人にインタビューする
OB・OG訪問やインターンの時間を使って、以下のような質問を社会人にインタビューする方法もあります。
・1日の業務スケジュール
・仕事のやりがい
・入社前後で会社に対する印象がどう変わったか
・どんな人材と一緒に仕事をしたいと思うか
・今後の目標
ここで注意すべきなのは、「たくさんの質問を尋ねすぎない」ということです。社会人に対してインタビューができる時間は限られているため、常識の範囲内で質問しましょう。
これまでの経験をノートにまとめる
ある程度経験を積んできたら、得た情報や感じた内容をノートにまとめてみましょう。思考の整理や、今後するべきことの把握を進められるからです。
・業界・企業研究のデータ
・自己分析内の内容
・今後のスケジュール
上記のような内容をノートにまとめておくことで、就活に関する情報をいつでも確認できるようになるでしょう。「今まで頑張ってきた証拠がここにある」「このノートがあれば大丈夫」という精神的な支えにもなるはずです。
就活準備のよくある質問と注意点
最後に、就活準備を進めるにあたって多くの人が抱きがちな疑問点とその回答を注意点としてまとめていきます。すっきりとした状態で就活準備を進めたいなら、ぜひ参考にしてください。
インターンはいつから参加すべきですか?
インターンは、本格的な就活がスタートする前である「大学3年生の夏頃~」には始めておくといいでしょう。可能なら、それより前に参加してももちろんかまいません。
主な理由としては、なるべく早くインターンに参加することで、志望する業界の理解を深めて自分に合った企業を探しやすくなるからです。選考直結型のインターンに参加すれば就活をより早く終わらせることもできるので、できる限り早めに情報を調べておきましょう。
ES(エントリーシート)・履歴書の準備はいつから始めるべきですか?
採用選考に欠かせないESと履歴書は、大学3年生の秋頃に準備を始めるといいでしょう。というのも、選考が始まるぎりぎりに準備を始めてしまうと、添削をする時間が無くなってしまうからです。
大学のキャリアセンターなどを活用して書類の添削を受け、内容をブラッシュアップしていくことが求められます。そうすることで、結果的に質の高いESや履歴書を作成することができますよ。
面接で緊張しないコツはありますか?
人前で話すことが苦手な人や、緊張しがちな人は、とにかく練習と改善を繰り返すことが必要です。頻出質問とその回答をリサーチ・考案しておき、スムーズに面接が受けられるようにスキルを高めておきましょう。
また、より好印象な学生に見えるように、表情を明るくすることや背筋を伸ばすことにも配慮するといいですね。
なお、もしさらに実践的な練習に取り組みたいなら、大学のキャリアセンターや就活エージェントを利用して模擬面接を行うこともひとつのアイデアです。第三者に面接内容をチェックしてもらうことで、客観的な目線を持ちながら練習できますよ。
就活と学業の両立のコツは?
就活準備は、大学の授業や研究などと並行して行わなければなりません。これらを両立するためには、双方のスケジュールをまとめて管理することが大切です。どちらか片方のスケジュール管理のみが手薄になると、書類の準備や課題提出の締切が重なり、問題が発生してしまうかもしれません。
これだけでなく、「今、自分は何に優先して取り組めばいいのか」をはっきりさせて、優先順位を付けながらタスクを完了させることも重要です。これによって、無理なく就活と学業両方の準備を進められるでしょう。
OB・OG訪問のアポイントはどう取ればいいですか?
OB・OG訪問は、大学のキャリアセンターを通してアポイントを取ることをおすすめします。大学を経由することで、関連トラブルに巻き込まれることを回避できるだけでなく、正しいOB・OG情報を参考にできるというメリットがあるからです。
また、ゼミやサークルの先輩を通じてOB・OGを紹介してもらうケースもあるでしょう。どんな方法を選んだ場合も、OB・OGとメールをやり取りする場合は、「伝えたい内容を簡潔にまとめること」「正しい敬語を使い、言葉遣いに配慮すること」などが大切です。それによって、OB・OGに余計な負担をかけずに準備を進められます。
企業選びの軸の決め方を教えてください。
いろいろな企業に興味関心が出てきてしまい、なかなか企業選びの軸が決められない場合は、「自己分析を何度も行って、自分の価値観を明確にすること」が必要です。そして、その価値観に合った企業を見つけていくといいでしょう。
具体的に言うと、仕事内容、社内文化、入社後の待遇、キャリアアップの一例などをはじめとした「各企業の特徴」に優先順位をつけ、その内容に当てはまる企業を探していくのです。こうすることで、企業選びの軸が自然と固まっていくはずですよ。
就活時の服装で気をつけることは?
就活で企業側に良い印象を持ってもらうためには、TPOに合った清潔感ある服装を選ぶことが求められます。というのも、基本的な身だしなみができていない学生が入社後に大きく活躍する姿はイメージしにくいからです。 また、清潔感のアピールのために「爪や髪の毛のケアを行っておくこと」「華美なアクセサリーは控えること」も頭に入れておきましょう。
まとめ
就活を成功させるには、適切な準備を着実に進めておくことが大事です。今回ご紹介した内容を参考にして、できることから準備を始めてみてくださいね。ひとつひとつの準備が積み重なることで、みなさんの就活スキルがぐんぐんと伸びていくはずです。