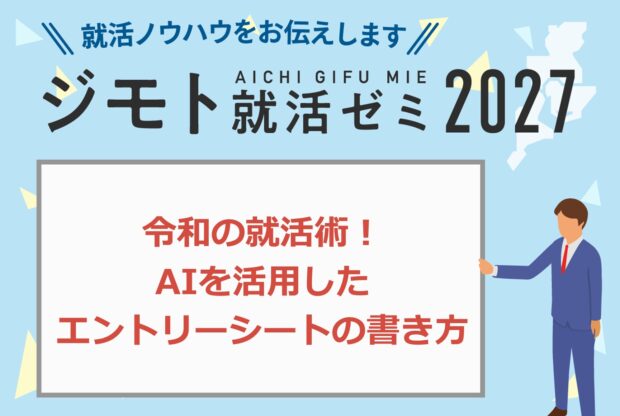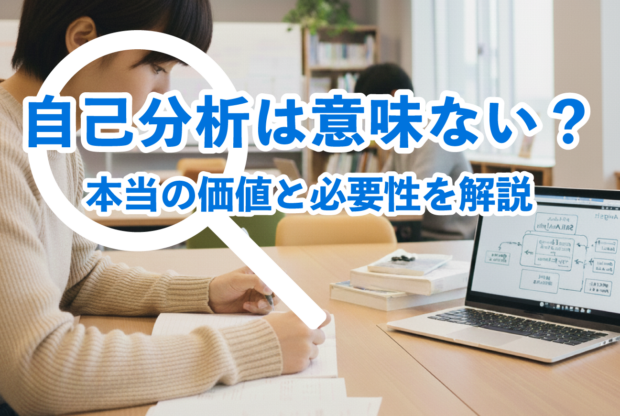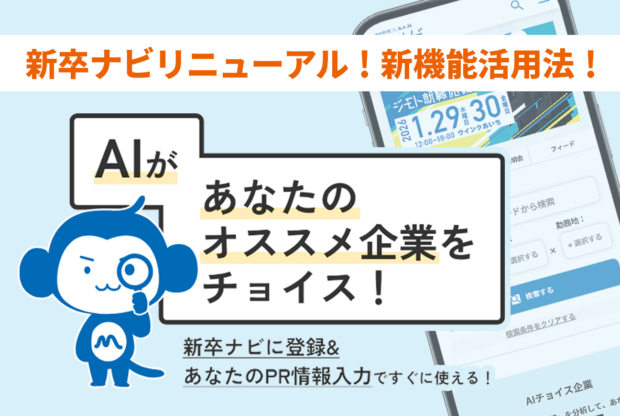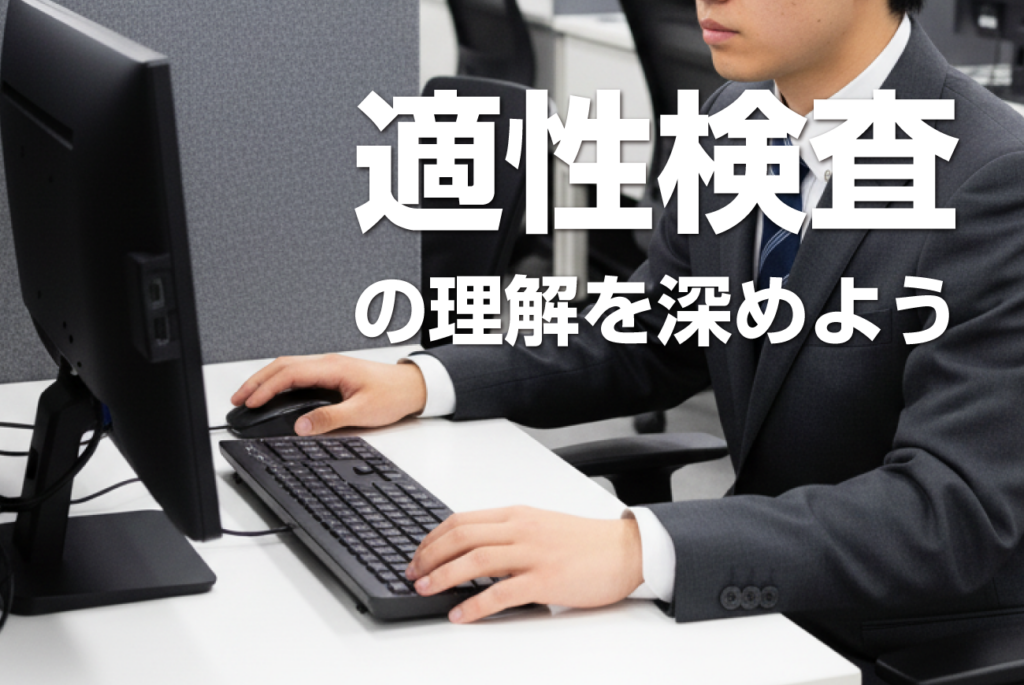
採用選考の1ステップとして、初期に実施されることの多い適性検査。企業によって実施する・しないは異なりますが、実施される可能性がある場合は対策をしておくと安心です。今回の記事では、「どんなことを評価するための検査なの?」、「内容は?」、「対策はどのようにすればよいの?」など、適性検査にまつわるよくある疑問に沿って解説したいと思います。
目次
まずは、業界や企業の選考ルートをリサーチ!必要であれば、早めに対策を始めましょう。
「どんなことを評価するための検査なの?」適性検査は、能力や人柄を知るための“参考資料”
採用選考の初期段階で実施されるのが「適性検査」は、応募者の能力や人柄を理解するための“参考資料”となるものです。実施の時期は、エントリー・説明会を終え、面接に進む前に行われるほか、一次面接の終了後、二次面接と間に行われるケースなどもあり、タイミングは企業によって様々です。
新卒採用を行う企業を対象に適性検査を実施する割合を調査したデータによると、実施企業が全体の70%台、80%台に上ります。高い実施率の背景には、検査の結果と入社後の適応に関係性があるかどうかが定期的に検証されていることも理由のひとつとして考えられます。また、多くの企業が、社内での選考だけでなく、客観的な情報に基づいた評価を採用に活かしたいと考えているのでしょう。昨今では規模の大小に関わらず導入する企業が増えています。就活生のみなさんは、一度は受検する可能性があると考え、心構えをしておく必要がありそうです。
「試験の内容は?」
SPI(※1)は、能力検査と性格検査の2本立て
適性検査は、作成・提供を行う企業が数社あり、それぞれに内容や実施方法が異なります。なかでもよく知られているのが、リクルートマネジメントソリューションズ社が開発した「SPI(Synthetic Personality Inventory)」。2023年度は15,500社の企業が導入、受験者数は217万人に上ります(※2)。本項目はこの「SPI」について説明します。
※1 2024年8月現在実施されているSPI3の検査内容に基づく
※2 参考:SPI公式サイトhttps://www.spi.recruit.co.jp/
まず、SPIには大きく分けて<能力検査>と<性格検査>の2つがあり、企業によっては付加的な検査である<構造的把握力検査>や<英語能力検査>が出題される場合があります。では、それぞれの内容について確認していきましょう。
能力検査とは?
能力検査は、スキルや知識を獲得する際のベースとなる基礎能力を測るもの。基礎能力は、あらゆる仕事に共通して求められるものです。試験時間は約35分、問題は「言語分野」と「非言語分野」の2種類が計70問出題されます。まず「言語分野」では、言葉の意味や話の要旨を的確に捉えて理解できるかどうかが問われます。主に国語の問題です。一方「非言語分野」は、数的な処理ができるか、論理的思考力があるかどうかを測るもの。数学的な問題です。
結果は、企業が求める能力水準を満たしているかどうかという観点で測られます。求める能力水準は企業によって異なるため、すべてにおいて高得点であればよいと一概に言うことはできません。
性格検査とは?
性格検査では、日頃の行動や考え方に関する約300問の質問が出題されます。試験時間は30分と、ややボリュームのある内容です。検査結果は、すべての解答を統計的に処理することで性格特性を割り出します。その内容に基づいて、人との関わり方や仕事に取り組む姿勢、目標の持ち方といった<その人の人となり>が示されることになります。
この検査を受ける際に注意したいが、自分をよく見せようと普段の行動や考え方と違う解答をしてしまうことです。企業が検査の結果を通して想定した応募者の性格特性と、本当の性格がずれてしまうと、「面接で話が嚙み合わなかった」「大事な面接を落としてしまった」という事態に。ここでは素直に直感的に回答するように心がけましょう。
構造的把握力検査、英語能力検査について
SPIでは、上記の2つの検査に加えて、「構造的把握力」や「英語」の検査が追加されることがあります。この二つは、SPIの軸となる「能力検査」「性格検査」のオプションと捉えると分かりやすいでしょう。
「構造的把握力検査」は、小・中学生レベルの文章を読み解き、構造が似ているものを分類するテストです。能力検査と同様、言語系と非言語系の2種類の問題があります。物事の背景にある関係性や共通性を見つけ出す問題を通して、問題解決力や論理的思考力を測るのが目的です。実施する企業は、総合商社や広告業界、不動産業界、コンサルティング業界に多い傾向です。
「英語能力検査」は、英語能力の基礎となる語彙・文法の理解力や文章の読解力を測定するもの。語彙力を問う問題のほか、英文の穴埋めや長文読解が出題されます。こちらは、外資系や総合商社、メーカーなどのほか、海外で事業を展開している企業で実施されています。
「対策はどのようにすればいいの?」
市販の参考書や問題集のほか、就活支援サービスを活用しよう
SPI(とくに能力検査)は、中学・高校生レベルの問題で構成されています。驚くほど難しい問題ではないと思うかもしれませんが、高校卒業して以来、一度も取り組んだことのない問題を解くことになる可能性もあります。高得点を目指すためには、やはり対策をして本番に臨むのが安心です。
勉強をスタートする前に、志望する業界や企業で例年SPIが実施されているか否かについてリサーチしてみましょう。可能であれば、構造把握力や英語の検査があったか否かについても情報が得られるとよいですね。就職フェアの企業ブースで思いきって聞いてみるのもいいですし、大学のキャリアセンターや卒業生から情報を得られるかもしれません。身近に教えてくれる人がいないか、ぜひ探してみましょう。もし情報が得られなかった場合は、実施される可能性に備えて対策するのが無難です。
効果的な勉強方法は“問題集1冊マスター作戦”がおすすめです。これまで聞いた就活生の体験談で一番よく耳にしたのがこの方法。書店で問題集を1冊購入して、まずはひと通り取り組みます。次は間違えた問題だけ取り組み、さらにもう一度最初から最後まで取り組みます。自分がこれで大丈夫だと自信が持てるまで繰り返すのがポイントです。問題集1冊をマスターできたら、本番の緊張感を味わうために模試を受けるのもよいでしょう。
ただし、限りある時間の中で、優先したいのは自己分析や企業研究。通学時間や寝る前などのすきま時間も活かしながら、高得点を目指せるとよいですね。

受験方法は、企業指定の方式で
SPIの実施方法は、応募企業によって異なるため、各社からの説明や指示に注意深く目を通すことが必要です。専用会場のパソコンで監督者の監督のもと受検するテストセンター方式や、自宅や学校などのパソコンから受検するWEBテスティング方式、マークシートで受験するペーパーテスティング方式などがあります。
玉手箱やGABなど、SPI以外の適性検査について
「玉手箱」や「CAB・GAB」といった適性検査を実施している企業もあります。玉手箱は、金融業界をはじめ、幅広い業界で採用されています。「CAB」はIT企業、「GAB」は総合商社などが多い傾向です。これらの適性検査にも対応する問題集が市販されています。SPIと同様に、まずは1冊に集中して取り組むのが効率よく対策するコツです。
最後に
適性検査の対策は、就職活動が解禁になる3年生の3月より前に、できるだけ早い段階から着手しておくのが安心です。SPIは、就活生の仲間と一緒に取り組むのもおすすめです。進み具合や弱点などをお互いに情報共有しながら進めていくと、モチベーションも上がります。